|
|
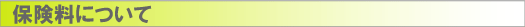 |
|
|
| |
|
|
後期高齢者医療制度は、被保険者と現役世代(74歳以下)のみなさまが支えあう仕組みになっています。
運営に必要な経費(医療費)は、被保険者が病院や薬局などの窓口で支払う「窓口負担額」(所得に応じた負担割合1~3割)と、保険から給付する「医療給付費」とで構成されています。
「医療給付費」のうち、約5割を公費(国・県・市町村)、約4割を現役世代からの支援金、残りの約1割を被保険者の保険料で賄っています。
みなさまに納めていただく保険料は、後期高齢者医療制度の運営のため大切な財源となっています。
後期高齢者医療制度では、被保険者となる方全員が個人単位で計算された保険料(年額)を納めます。保険料(年額)は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額です。
保険料(年額)を算出するための「均等割額」と「所得割率」のことを「保険料率」といいます。この保険料率は沖縄県内で均一です。
なお、保険料率は2年ごとに見直しを行います。
令和6・7年度の保険料率は、令和6年第1回沖縄県後期高齢者医療広域連合議会(令和6年2月2日)で可決されました。
|
|
|
(1)令和6・7年度の保険料率は次のとおりです。
(参考)令和4・5年度保険料率等との比較
| 保険料率 |
令和6・7年度
(A) |
令和4・5年度
(B) |
比較
(A-B) |
| 均等割額 |
56,400円 |
48,440円 |
7,960円増 |
| 所得割率 |
11.60% |
8.88% |
2.72ポイント増 |
1人当たり
平均保険料額
(軽減適用後) |
R6 96,861円
R7 98,887円 |
78,409円 |
R6 18,452円増
R7 20,478円増 |
※基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度に限り10.18%の所得割率が適用されます。
※1人当たり平均保険料額(軽減後)は、保険料改定時の見込額です。
(2)保険料賦課限度額
保険料には「賦課限度額」が設けられています。
【保険料の激変緩和措置について】
令和6年に制度改正が行われたことによる保険料の急激な上昇を緩和するため、以下の激変緩和措置が講じられています。
※沖縄県では、制度の見直し以外の要因(人口構成の変化や医療費の増加等)により、保険料額が増加しました。
・基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入211万円相当)以下の方の所得割率は、令和6年度に限り10.18%が適用されます。
・賦課限度額の引き上げは、令和6年3月31日時点で75歳以上の方及び令和7年3月31日以前の障害認定による加入者(当該認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった方を除く。)を対象に令和6年度は73万円、令和7年度は80万円と段階的に実施されます。
|
詳細については、制度見直しのリーフレットをご覧ください。
後期高齢者医療制度の見直しに関するお知らせリーフレット(厚生労働省)
|
| |
| [ 上に戻る ] |
|
|
保険料(年額)は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額です。
年度の途中に資格を取得または喪失した場合は、月割りで計算した保険料となります。 |
保険料(年額)
限度額80万円(※1)
|
= |
均等割額
56,400円 |
+ |
所得割額
[総所得金額等-基礎控除額]
×11.60%(※2) |
(※1)昭和24年3月31日以前に生まれた方、または令和7年3月31日までに障害認定により被保険者資格を有している方の賦課限度額は、令和6年度に限り73万円になります。
(※2)令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を以下の方の所得割率は、令和6年度に限り10.18%となります。
|
| 総所得金額等に含まれる主な所得金額 |
| 総所得金額 |
他の所得と区分して計算される所得金額 |
・年金所得(年金収入-公的年金控除額)
・給与所得(給与収入-給与所得控除額)
・農業所得
・営業所得
・不動産所得
・雑所得(生命保険の年金、暗号資産取引等)
・一時所得 など |
・山林所得
・株式、土地・建物の譲渡所得
・先物取引に係る雑所得等
・上場株式に係る配当所得(申告分離課税分)
・土地等の事業所得の金額(申告分離課税分)
・特例適用利子等、特例適用配当等
・条約適用利子等、条約適用配当等 など |
|
| 〇退職所得、非課税所得(遺族年金・障害者年金・失業給付など)は含まれません。 |
|
基礎控除額について
|
|
合計所得金額
|
基礎控除額
|
|
2,400万円以下
|
43万円
|
|
2,400万円超~2,450万円以下
|
29万円
|
|
2,450万円超~2,500万円以下
|
15万円
|
|
2,500万円超
|
0円
|
|
| |
| |
所得の低い方に対する均等割額の軽減と、被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者であった方に対する軽減の制度があります。
(1)所得の低い方に対する均等割額の軽減
世帯(世帯主と被保険者)の所得水準に応じて下表のとおり均等割額が軽減されます。
|
同一世帯の世帯主および被保険者の総所得金額等の合計額
|
軽減割合
|
軽減後
均等割額
|
| 43万円+10万円×(年金・給与所得者数※-1)以下の世帯 |
7割軽減
|
16,920円
|
43万円+30.5万円×世帯の被保険者数
+10万円×(年金・給与所得者数※-1)以下の世帯 |
5割軽減 |
28,200円 |
43万円+56万円×世帯の被保険者数
+10万円×(年金・給与所得者数※-1)以下の世帯 |
2割軽減
|
45,120円 |
※年金・給与所得者数とは、同一世帯の世帯主および被保険者のうち以下のいずれかに当てはまる方の合計人数です。
・65歳未満で公的年金収入が60万円を超える方
・65歳以上で公的年金収入が125万円を超える方
・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える方
〇1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。
〇世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合、その世帯主の所得も軽減判定の対象になります。
〇軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は、加入した日)の世帯の状況で行います。
〇事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
(2)被用者保険の被扶養者であった方への軽減(国保、国保組合の方は除く)
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合、共済組合など)の医療保険の被扶養者であった方は、加入から2年を経過する月まで保険料の均等割が5割軽減され、所得割額は課されません。
| 後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった方 |
均等割額 → |
5割軽減(加入後2年間) |
| 所得割額 → |
負担なし |
※低所得による均等割額軽減の対象になる方は、軽減割合の大きい方(均等割額7割軽減)が優先されます。
※国民健康保険や国民健康保険組合は対象となりません。
|
| |
| [ 上に戻る ] |
(3)保険料の計算例
○夫婦二人世帯の年金収入で、妻の収入が80万円のモデル世帯
|
|
公的年金収入額
|
均等割額
|
均等割
軽減割合
|
所得割額11.60%
|
合 計
|
1月当たり
|
|
1
|
夫
|
168万円
|
16,920円
|
7割軽減
|
17,400円
|
34,320円
|
2,860円
|
|
妻
|
80万円
|
16,920円
|
7割軽減
|
-
|
16,920円
|
1,410円
|
|
2
|
夫
|
227万円
|
28,200円
|
5割軽減
|
85,840円
|
114,040円
|
9,503円 |
|
妻
|
80万円
|
28,200円
|
5割軽減
|
-
|
28,200円
|
2,350円 |
|
3
|
夫
|
277万円
|
45,120円
|
2割軽減
|
143,840円
|
188,960円
|
15,747円
|
|
妻
|
80万円
|
45,120円
|
2割軽減
|
-
|
45,120円
|
3,760円 |
|
4
|
夫
|
281万円
|
56,400円
|
軽減なし
|
148,480円
|
204,880円
|
17,074円
|
|
妻
|
80万円
|
56,400円
|
軽減なし
|
-
|
56,400円
|
4,700円 |
|
|
|
保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収に分かれています。
(1)特別徴収
年額18万円以上の年金を受け取っている場合は、年金から保険料が天引きされます。
※介護保険料が天引きされている年金が対象です。介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合には「普通徴収」となります。
(2)普通徴収
特別徴収以外の方については、納付書や口座振替等の方法により、お住まいの市町村に納めていただくことになります。
【保険料を滞納すると】
納期限を過ぎても納付がない場合、法令に基づき督促状が送付されます。また、納期内に納付された方との公平性を図るため、延滞金が加算される場合があります。
滞納が続くと、電話や文書、訪問による催告が行われます。特別な理由がなく保険料を滞納した場合には、滞納処分(財産の差し押さえ)の対象になります。
納付が困難なときは、お早めに市区町村担当窓口にご相談ください。
【保険料の減免制度】
災害など特別な事情により保険料の納付が困難な時は、一定の基準を満たせば、保険料の減免の適用を受けられる場合があります。
お早めにお住まいの市町村窓口にご相談下さい。
|
令和7年度の制度見直しに関する厚生労働省コールセンターの設置について
|
|
後期高齢者の医療費は、窓口負担を除いて約4割が現役世代の負担する支援金でまかなわれています。少子高齢化が進む中、後期高齢者の医療費は今後さらに増えていくと見込まれています。このため、全ての国民が、年齢に関わりなく、その負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことが重要となります。このような考えに基づき、後期高齢者医療制度の保険料について令和5年に法律改正が行われ、令和6・7年度の保険料に反映されています。令和7年度の制度見直しに関する厚生労働省コールセンターについて、以下のとおり設置いたします。
- 【設置期間】令和7年7月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)※日曜日、祝日、年末年始は除く
- 【対応時間】午前9時~午後6時
- 【電話番号】0120-117-571(フリーダイヤル)
※ なお、マイナ保険証や資格確認書に係る問い合わせについては、引き続きマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にて承ります。
|
| [ 上に戻る ] |
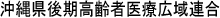 |
| 〒904-1192 沖縄県うるま市石川石崎1丁目1番(3F) |
| 【TEL】 |
098-963-8011(総務課・会計室) |
|
098-963-8012(管理課) |
|
098-963-8013(事業課) |
| 【FAX】 |
098-964-7785 |
| 【MAIL】 |
soumu@kouiki-okinawa.jp※@は小文字@に置き換えてください |
| 【URL】 |
http://www.kouiki-okinawa.jp |
|
|
|
|
|

